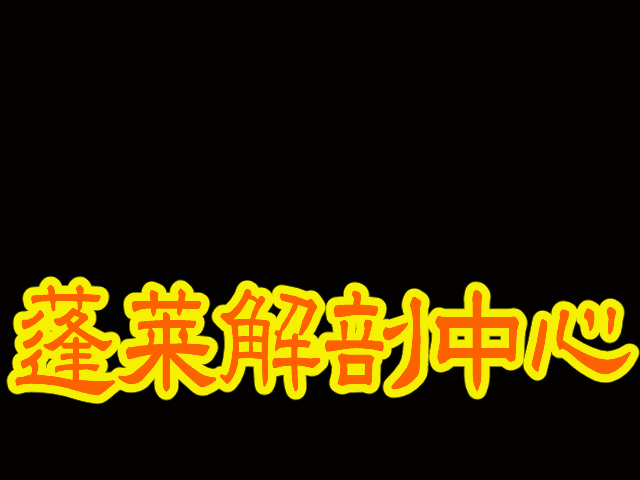
蓬莱レーヴシルクお疲れ様でした。
この記事を読まれた方は流石に錦上京を嗜んでいるかと思いますが、今回はなぜか陰謀論の部分がクリティカルヒットしてしまい複雑な気持ちになっている。どうすんだあいつ・・・
せっかくなので、記事のコメント紹介を行います。皆さんありがとうございました。
個別に返事は返しているので、コメントから改めて私が考えたことを並べてみます。
>最後の方にある蓬莱人形は最後にたどり着く作品って所にめっちゃ頷いた。私もそうだったから。最初の方に作られたのにみんなが最後に辿り着く楽園だね。本当に楽しい記事をありがとうございました!!
これ本当にそうなんだよな。しかもなんか、ある程度狙っている気がする。
確かに、(ある意味)最初の作品が(ある意味)最後の作品になる、というのはかなり面白い感じだと思うが、これも作るの難しすぎると思う。誰も未来がわからないから。
それができているとするなら、紅魔郷の前に5作作れていたことと、永夜抄あたりを区切りにすると決めていたから展望を持ちやすかったことが原因だと思う。倍以上続いていることだけが想定外だったのだろうか。
>私、98版より先に蓬莱人形だったなぁ。なんだかんだ今(10年前)でも手に入るかどうかの違いは大きい
こういう方もいる。なんで旧作が蓬莱より先に視界に映りがちかというのは、東方がキャラゲー文化であることと、自分たちの世代だとBadappleの存在が大きいと思っている。
あと、多くの人はシリーズを好きになるとき、結構その最初から追いたくなりがちで、そういう視点から見た最初の作品というと、紅魔郷より靈異伝が上がる気がする。プロトタイプとか好きがち。
今でも流通しているのはありがたいこと。本当にありがたいことですね。
>当時神主は最初はサウンドトラックを出す予定だったそうで、Complete Darknessなどを収録する予定だったようです。
ここで推測なのですが、このサウンドトラックは原曲そのものではなく、いわゆるアレンジバージョンサウンドトラックだったのではないかと思われるのです。
その為に、納得いかなかった曲の差し替えなどがC62合わせで行われて曲目が変わった可能性があります。
なんかいただいたこのコメント以外にもイベント後にも視界に入った情報だったけど、結局ソースが観測できていない。ご存知なら教えて下さい。
オーエンに差し替わった可能性が高いが、完全に無根拠で難しい。プロトタイプとか、好きがちだから。
>怪文書面白かったです!共感の嵐
面白さ1-aあたりが特に共感で、東方毎回新作出るたびに「ア!このモチーフは蓬莱時代のあの題材への再チャレンジだろうな!」ってなりますよね これは面白さ4にも片足を突っ込んでいます
語りたくなる記事をありがとうございます!
私は蓬莱人形の桜花之恋塚のプレス版テキストが好き!
ありがとうございます!
根としての蓬莱人形、味がなくならないからすごい。
ちなみにおれが好きなテキストの箇所は初版の東方怪奇談です。
>文章読ませていただきました。
自分は長く東方ファンをしていますが、蓬莱人形についてはあまり触れてこなかったので、この謎の多い作品がどういうものなのか解説してくださるのは、とてもありがたいことです。
初見では、音楽の良さもイマイチわからなかったのですが、初見からおよそ8年くらい経って、ようやく音楽の良さを理解できました。
まだ世界観を楽しめるほどには浸かっていませんが、このイベントには多くの熱狂と想像が具現化されていて、それを眺めるのは楽しいです。
ありがとうございます。
これほんとに嬉しくて。読みづらい文章を読んで頂き、本当にありがとうございます。
音楽を一周するだけじゃ、全然わからないんですよね。おれもそうだった記憶がある。
世の中には消費すべきコンテンツが星の数ほどあるのに、聞き流さずにふと立ち止まったところに深い穴がある。
別に蓬莱人形に限った話ではないと思うが、すべてのコンテンツがそうであるとは思わない。
自分も可能であれば、深い穴を掘ってみたい。そう思います。
>読むのを楽しみにしていました。蓬莱人形の面白さ、本当に語るのが難しいと思っているので、あづれさんの言語化を通して改めて向き合えるのが本当にうれしいです。
特に②は一言一句同意でした。脈絡ない文章と音楽の集合体のようでいて、過去未来のあらゆる文脈を想起させ、水面下で生き物のように変化し続ける作品、面白すぎる...
ありがとうございます!
こんな感じで感想をいただくにはもったいないくらいのやっつけ文章でしたが書いた甲斐がありました。
味のなくならないコンテンツ、怖(二度目)
味がなくならないので、その無限の力をどうラーニングするかは今回追おうとして全然無理だったのですが、記事を通して「そういう視点」を持ってもらう試みは成功したかもしれません。
おれは無理っぽいので次の世代につなぎます。試みがうまく行ったらこっそり教えて下さい。
こんにちは、あづれです。いつもお世話になっております。
蓬莱レーヴシルク、開催おめでとうございます。
私からは、「おれは、蓬莱人形の何を面白く感じているのか」「蓬莱人形の面白さを読み解き、活用を見いだせる部分はないのか」などといった文章を、自身の覚え書きと夏休みの自由研究(夏休みの自由研究?)を兼ねて、文章にまとめてみようと思います。
(蓬莱レーヴシルクから来た方へ)よければサークルの掲示板のところに、「私は蓬莱人形のこういうところが好き!」という情報をコメントください!
内容の一部はこの記事かSNSでも紹介しようと思います。怖くないです!よろしくお願いします!
1 はじめに、たくさんの言い訳を書くので読み飛ばしてください。
2 あづれの蓬莱人形に関する経歴。しがみつき具合。
以上の経歴から見えることは、蓬莱人形に関する楽しいイベントは長期間にわたり散発的に起こっていること、また私個人で解決するというよりは、属していた小規模なコミュニティの中でそれぞれが課題を出したり解決したりしていたということでしょうか。
いつもありがとうございます。
本題に入る前に、蓬莱人形についても短めにまとめましょう。
難しいところだが、一旦記憶喪失した体にしてCDを見て、聴いてみることにする。
以上。記憶を戻しました。楽しかった。
改めてまっすぐ音楽に向き合うと、アルバムの雰囲気からずらした音楽も込みで、すごく綿密に構成された曲目だと思う。
聞いている人を不思議の国に誘い込み(「穴」を彷彿とさせる画像も相まっている)、暗くて怖い世界を歩かせて、闇を祓う。アトラクションのような印象かも。
蓮台野夜行以降は明確に「秘封倶楽部」の物語としてこの手腕が発揮されるわけだが、蓬莱人形ではあえてキャラをぼかし匿名性を強めることで、聞いている自分自身にフォーカスが当たるようになっている。気がする。
序盤は優しく、心強い印象、中盤は暗く、催眠状態のような印象、終盤は恐ろしく、清々しい印象。最後の曲、最後のフレーズがとても重く、聞いたあとも黙って考え込んでしまう。そういう奥深さがある。
問題は、音楽だけでここまで語ったが、まだ初版のブックレットや取り巻く世界観について全く話していないことにある。長い記事になりそうです。
全曲聞き終えた後で、改めてキャラクターを見てみる。ジャケット子とレーベル子の話です。
いやもう美しい。曲を聴く前は地味なジャケットだと思うかもしれないが、なんだろうこの美しさは。しかし名前がない。どういうことだ。
初版ブックレットについては正直まるごと言及を控えたいと思っていた。
蓬莱人形は、CD単体で語るのが難しいというのが持論。
東方Projectの作品群と密接に関わっていることや、CDに込める意思がその後の作品にも通じている(通じている?)だろうと思われるため。
個人的に面白いなーと思うところの一つが、蓬莱人形が登場した時点では蓬莱人形は決して「セピア色の過去」ではなく「最新の音楽」だったところ。紅魔郷以降のゲームは存在しないし、靈異伝から稀翁玉の音楽しかレパートリーには存在していない。
有名な話だけど、収録曲の「明治17年の上海アリス」が蓬莱人形のオリジナルと明記されている一方、「U.N.オーエンは彼女なのか?」にはその表記がなく、紅魔郷が初出扱いになっている。(https://www16.big.or.jp/~zun/html/hr01.html)
C61時点では音楽サークルとして応募していたところ落選し、C62でゲームと一緒に頒布したという経緯が知られており(https://www.4gamer.net/specials/shanghai_alice/zone_z.shtml)、蓬莱人形のほうが紅魔郷より先に作られていたというのが通説だが、それだとオーエンが収録されているのは謎であり、明確な答えもなかったはず。
要するに何が言いたいかというと、紅魔郷と蓬莱人形は並行して生み出された作品であり、表裏一体であるということ。
作者が残しているWebを巡るのは本当に楽しい。本当に楽しいコンテンツです。
(https://www16.big.or.jp/~zun/html/profile.html)
ちょっと待ってください。25年前のプロフィールページをみんなで喜んで見るのはどうなのか。
しかし残されていることは本当にありがたいことだ。紹介されている作家はどれに当たっても非常に面白く、奥が深く、蓬莱人形の一端を知ることができる。
自分が直接触れたのは、記事の中では松居慶子、藤木稟、小野不由美、竹本泉、山田章博くらいか。記事の外では、STGは遊べるだけ遊んでる。あとYMO。正直不勉強だと思う。
このままでは私の集中力が切れ、蓬莱人形のソース紹介記事で終わってしまいます。これではだめ!!方針転換しましょう。
この記事は「おれが考える蓬莱人形の面白さを解剖する」のがメインです。そして今まで書いていた文章もそのまま乗せて記事を方針転換します。
そういうことが、できる。個人サイトだから。
この情報量についてまず語りたい。
上記に色々書いてきたものの、正直全然要素を拾いきれていないと思う。
まだ西方の話してないし、音楽の理論や画像素材、元ネタについても掘り下げてないし和洋折衷の珍しい世界観についても語れていない。既存のキャラクターや、蓬莱少女繪に隠された情報も語ってない。非常に多いんです。
そもそも、幻想郷についてほとんど語っていない。今視聴する人はWin版東方のその他の作品を一通り嗜んだ後に楽しむ流れになっているはず。
「情報が多い」だけだと、ただ情報量が多いだけの作品になってしまうのだが、他と違うところを考えてみる。
蓬莱人形が他と違う作品である点として、「Win版東方Projectの最初の作品でありながら、最新作まで思想が受け継がれている」という点かもしれない。
幻想郷という閉鎖された空間で人形劇のような演出は作劇上の都合ではなく、仕組まれたものだ。巫女服が巫女服らしくないのも、東方に直接的な死がほとんど表現されないのも、蓬莱人形というベースがあるからこそ、だと思う。
要するに、蓬莱人形は東方の思想を根幹から支える根のような役割であり、枝葉が茂るほど根は深く潜っていく。
完結した作品ではそうはいかない。いくら情報が多くても吹きざらしの路地に立たされたら、あっという間に劣化していく。東方Projectと表裏一体であることによって、見たこともない大きさになっていく、気がする。
言葉だけでいうと、蓬莱人形の楽曲が旧作や西方からのリマスターであり、紅魔郷を支点として未来につながる思想が同時に過去とも繋がっている、ということが言いたい。
蓬莱人形がなければ、俺が一生知ることのなかった作品は多いかもしれない。
多分旧作は把握していたな。十二国記は知らずに終わっただろう。
西方も、多分ここまで好きにはならなかったかも。
未来方向で考えても、初期トリロジー(紅~永)は蓬莱人形の永遠性(刹那性)をテーマに持ち、花映塚で完成させている。先述したように、思想は一部現在に引き継がれている。
これは俺からの視点であり、歴史的な背景とは真逆なのだけれど、東方を始めるとき、見かけた作品から始めて、Win版を順に追い、旧作を追い、最後に触れるのが蓬莱人形な気がする。
「最後の作品」というには最初すぎるわけだが、最後の作品だと思って楽しんでも遜色ないような作りをしていると思う。
前述の「パイプである」「情報が生きている」とは相反する気もする。どう思いますか?
隠喩・象徴的表現が何よりも好き。不勉強で申し訳ないけど…
エンタメとしての作品に隠喩を込めるのはどうも難しいらしく、やはり読み解くのに時間がかかるからだろうか。
蓬莱人形というより東方が既に抽象表現のオンパレードで、原作がSTGなのでストーリーよりも弾幕でキャラクターの精神世界やフィールドを表現してるところが好き。スペルカードは隠喩の観点からもすごい発明だと思う。
なぜ隠喩・象徴的表現が私の健康に良いのか。時間をかけて考えてみたけど、「復号化する必要のない暗号」だから、とか、現実では起こり得ない表現が好きだから、とか、難しいことを考えるのがすきだから、とか、色々ある気がするが、正直明確な答えは出てこなかった。
隠喩・象徴的表現にまみれた創作物の情報は、常にお待ちしています。
https://www.pixiv.net/artworks/63240232
やっとここで世界観の話…
一番簡単なはずなのに書くのが難しく、難航しています。
逆に聞きたいのだけど、皆さんは蓬莱人形のどういう世界観が好きですか?
俺は、本来閉塞的で平和であるはずの幻想郷が、産み落とされたタイミング(幻想郷が幻想郷という名前になったのは蓬莱人形・紅魔郷が初めて)で既に血で塗れたものであり、楽園(パラダイス)は憂鬱がなければ生み出されない概念だと言うことに気付かされるという表現が好きだと思う。まず最初はそうだった。偽の楽園の人形たち。
正直者の話にも触れておきましょう。8人の正直者、チームプレーに見えて自分のことしか考えていないような感じがするのも好き。隠喩的な表現すらほとんどない恋愛感情の暴露とかも好きだ。嫌いな人はあまりいない。
未熟で憂鬱な正直者に感情移入することができれば、永遠の巫女でたいへんびっくりすること間違いなし。結局何もわからないまま帰ることができない感覚に陥る。すごいよね。
次点で好きになったのが、シルクロードの概念で、完全な妄想であるのだが「正直者はどこから来たのか」などが、魔界とユーラシア大陸で重なって表現されている気がするところ。
個人誌として作ろうと思っているが難航中。いつ作ることやら・・・。
正直これはすごく主観的だと思う、というか今までもそうだけど!!!
要するに蓬莱人形が、東方をめぐるあらゆる要素に絡んでいる気がしてきており、あらゆるものは蓬莱人形に行き着くという発想に陥る。本当にそうなんです。
ここまで悟ってしまうとファン同士お互いに語ることが減ってくるというか、異様な熱気に包まれるので、もうめちゃめちゃ楽しい。今のインターネットで最も恐れられているエコーチェンバーのような空気を、結構前までは楽しんでいたところがある。
かといって俺は陰謀論に耐性があるんだ、とは口が裂けても言えるものではない。
本当にみなさん正気を失うのは創作物の中だけにしましょう。
蓬莱人形の主観的面白さは、単純な創作物の一つという枠組みを遥かに超えた、極めて多岐にわたるものであり、ゆえに今まで文字に起こすのが難しく、再現性も低いものだと思っている。
蓬莱人形自体が東方と表裏一体であるため、1枚のCDには収まりきらない異常な情報量が含まれており、その事実そのものが面白いのに、中身を一つ一つ読み解いていくと別個の面白さが湧き出てくる。 それはそれとしてCDそのものも何度も聞ける剛性がある。
ここまで読んでくださった方、ありがとうございます。「自分の考えてる面白さが書かれてないのだが・・・・・・・・・」と思いましたか?そう。書き漏らしているのです。多すぎて。
今までの撒き散らされた散文を読むに、「蓬莱人形と同じ種類の面白さの再現性は極めて低い」ことがわかると思います。そうですよね。
例えばこれが大手出版社の編集会議だったとき、俺は蓬莱人形の面白さをもっとずっとわかりやすく表現し、エッセンスを抽出し、理解して貰う必要がある。これができるかという話です。
絶望的なのはわかりきっているが、なるべく頑張って書いてみます。
これが最も再現性に欠けると思う。
この土台を作るのは簡単じゃない。
例えば・・・直接再翻訳するなら・・・
異世界転生系の話だとして、比較的優しい雰囲気物語を走るのと並行で、名言は避けつつ、その中に仕込ませる形で作者の暗い意思を混ぜ込んだサイドストーリーを展開する…?
いや難しいよな…問題は大前提として、表の物語がめちゃくちゃおもしろくて成功している体を取る必要があるし、裏の物語も公然の事実扱いだとニュアンスが変わってくるよな
自分が知っている近い感じの物語だと、遊戯王ARC-Vの主人公か・・・
知ってる人は知ってる賛否両論の問題作なんだけど、主人公の遊矢が闇落ちしていく過程は表情から読み取れなくて、使用するカードがそれとなく「悪」寄りになっていく表現があり、感心して見ていたのを覚えている。ただそれって全然蓬莱人形的ではないよな。
とにかく、このタイプの「面白さ」については、それに触れたユーザーの解釈に委ねられていて、作者側で誘導するのは難しいし、それだけ蓬莱人形が変わっているという点かもしれない。
ないのかな・・・こういうやつ・・・
隠喩や象徴表現は物語の根幹にならない。
いや、実はなるのだけど(俺はそういうのが好き)、蓬莱人形や東方においてはそうではない。
ポイントは「ゲーム」や「音楽」というメインのコンテンツがあり、それらに組み込まれているという点が特徴的か。
これについては、ある程度再現できる気がする。
漫画や小説は比較的組み込みやすい。楽しいと思う。音楽は最近難しいかも。ブックレットが絶滅の危機なので。ゲームはいけるな。そういう作品大好きです。
ぜひ増えてほしいところ。
自分でもよく想像したりするのだけど、難易度が高いなと思うのは、150年くらい前の外国が舞台だとすると、調べるのが難しいところ。それなりに調べたつもりだけど、キャラクターを中に入れて動かすくらいまでこなれていない。できる人はすごいと思う。
音楽については、1枚のCDの曲が世界観に合致するように作るのが結構難しそう。あと、暗く激しいだけではだめなんだよね。素人なので全然語彙がない。
「流行っちゃいけないタイプの面白さ」すぎるだろ。
でも面白さって常にそういう危うさを内包している。まっすぐ考えてみよう。
自前の作品に対する都市伝説的な志向なのが蓬莱人形で、これをまるごと再現するなら前述のように「大きな表の世界を作る」という手順から「裏の世界を準備する」という感じになるが、何度も書いてるとおり、とっても難しい。
例えば既存の別作品に対する新たな解釈を提示する「裏の作品」みたいにするならありかもしれない。標的にされた「表の作品」はめちゃ迷惑だと思う。やるなら自前の作品でやりたい。
お疲れ様でした。そろそろ限界。
最初から「怪文書です」と宣言していただけあり、非常に読みづらい文章でした。すみません。
自分の考える蓬莱人形の面白さを少しでも共有できていたら嬉しいです。
「は?言ってる意味わからんし、俺のほうがもっと言語化できるわ!」と思ってくださったら、もっと嬉しいです!!書いて!!
改めて、蓬莱人形が持つ底知れなさと、異常な風化耐性に驚かされることになった。
まだ全然書けてないんだよな…キャラクターやステージが、どれだけ蓬莱人形に関連しているかとかも話すと長いですよね…
全然関係ないけど、今回はMarkdown記法を使い、Obsidianから編集しています。
他の記事に比べて段落やリストがわかりやすくなっているはず。簡単なので引き続き使っていきたい。
最初にも書きましたが、コメントお待ちしています。
またお話しましょう!元気でね~!